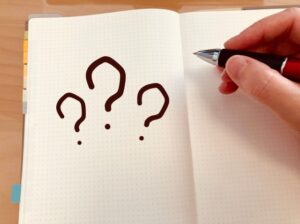受付時間:平日9時〜19時
高額介護サービス費と高額療養費制度が相続財産になる理由

相続が発生した際、預貯金や不動産などの資産に目が向きがちですが、実は高額介護サービス費や高額療養費制度の未支給分も相続財産に含まれることをご存じでしょうか。これらの制度は、介護や医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、その超過分を払い戻す仕組みですが、被相続人が生前に申請していたものの、支給前に亡くなった場合、その未支給分は請求可能な財産として扱われます。したがって、相続人は必要な手続きを行うことで、正当に受け取る権利を持つのです。しかし、請求期限が設けられているため、迅速な対応が求められます。本記事では、これらの制度の仕組みや未支給分が相続財産となる理由について詳しく解説し、相続手続きの際に注意すべきポイントを紹介します。
高額介護サービス費と高額療養費制度とは?
高額介護サービス費の概要
高齢者が介護保険サービスを利用する際、自己負担額は1割から3割に抑えられていますが、長期にわたると負担が大きくなります。そこで導入されているのが高額介護サービス費という制度です。この制度では、1か月の自己負担額が所得に応じて定められた上限額を超えた場合、その超過分が払い戻されます。たとえば、住民税非課税の世帯では月額15,000円、一般的な所得の世帯では44,400円が上限となっています。このように、利用者の経済状況に配慮した仕組みとなっており、申請を行うことで払い戻しを受けることができます。ただし、自治体ごとに手続きの方法が異なるため、必要書類や申請期限を事前に確認することが重要です。
利用者負担の上限(1か月あたり)
| 利用者負担の上限(1か月あたり) | |
| 利用者負担段階区分 | 限度額(世帯合計) |
| 生活保護の受給者など | 15,000円(個人) |
| 世帯全員が市町村民税非課税かつ 老齢福祉年金受給者 公的年金等の収入金額と合計所得金額等の合計が80万円以下の方 | 15,000円(個人) |
| 世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円 |
| 課税所得380万円未満 | 44,000円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 |
| 課税所得690万円以上 | 140,100円 |
名古屋市ホームページ
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/seido/hutan/kogaku.html より
高額療養費制度の概要
高額療養費制度は、医療機関での診療や入院にかかった自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、超過分が払い戻される仕組みです。公的医療保険(健康保険や国民健康保険)に加入している人であれば、誰でも利用することができます。公的医療保険加入者は、医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じて、1割~3割となっています。そのため、病気やケガで医療費が発生しても、私たちはその一部を負担すれば済みます。自己負担割合が3割の人が100万円の医療を受けたら30万円の支払いになるかというとそうではありません。自己負担額には上限が決められています。上限額は年齢や所得に応じて異なり、たとえば70歳未満の一般的な所得の人は月額57,600円、住民税非課税の高齢者は月額8,000円と設定されています。病院の窓口ではいったん支払うも、その後払い戻しを受けられます。
さらに、同じ世帯内で医療費を合算できる世帯合算の仕組みや、短期間に高額な医療費が発生した場合に自己負担限度額が引き下げられる多数回該当といった制度もあります。申請しないと払い戻しを受けられないため、加入している健康保険組合や自治体に手続き方法を確認し、適切に利用することが大切です。
未支給分が相続財産になる理由
被相続人(故人)の権利として確定しているため
高額介護サービス費や高額療養費制度の払い戻しは、被相続人(故人)が生前に申請を行い、その支給が確定している場合、相続人に引き継がれます。つまり、本人が受け取るはずだったお金が未支給のまま残っている場合、それは被相続人の権利として認められ、相続財産の一部となるのです。
未支給の給付金も「金銭債権」として扱われる
未支給の高額介護サービス費や高額療養費は、法律上「金銭債権」として扱われます。これは未支給年金と同様の考え方であり、相続財産として遺族が受け取る権利を持ちます。したがって、相続手続きの際には、未支給分があるかどうかを確認し、適切に請求することが重要です。
実際に相続人が請求できるケースとは?
相続人が未支給分を請求できるケースには、すでに申請が完了していたが、支給前に被相続人が死亡した場合が挙げられます。また、申請自体が行われていなかった場合でも、一定の条件を満たせば相続人が代わりに申請可能です。いずれの場合も、請求期限が定められているため、速やかに確認し、手続きを進める必要があります。
相続人が未支給分を請求する方法
未支給分の有無を確認する
相続が発生した際、まず未支給の高額介護サービス費や高額療養費があるかどうかを確認することが重要です。高額介護サービス費については、被相続人が住んでいた自治体(市区町村)の窓口に問い合わせることで、未払いの有無を調べることができます。一方、高額療養費制度に関しては、被相続人が加入していた健康保険組合(国民健康保険や社会保険など)へ問い合わせることで、未支給分があるかどうかを確認できます。
必要な書類を準備する
未支給分がある場合、相続人は所定の手続きを行う必要があります。その際、被相続人の戸籍謄本(死亡の事実を確認できるもの)、相続人であることを証明する戸籍謄本、そして各自治体や健康保険組合で配布される申請書を用意します。これらの書類が揃っていないと、請求手続きが進まないため、早めに準備を整えておくことが大切です。
請求期限に注意
未支給分の請求には期限が設けられているため、注意が必要です。高額介護サービス費および高額療養費の申請期限は2年以内と定められており、この期間を過ぎると請求権を失ってしまいます。そのため、相続が発生したら速やかに未支給分の確認を行い、期限内に手続きを完了させることが重要です。
相続手続きの際の注意点
遺産分割協議が必要になるケース
未支給分の給付金も相続財産の一部であるため、他の財産と同様に相続人全員で分割の話し合いを行う必要があります。特に、被相続人が生前に申請を完了していた場合、給付金は相続財産として確定しているため、遺産分割協議の対象となります。相続人間でトラブルを避けるためにも、事前に話し合いを進め、適切に分配することが重要です。
遺言書に明記も可能
未支給の給付金については、遺言書に明記しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることが可能です。例えば、特定の相続人に未支給分を相続させることを指定したり、遺言執行者を指定することで、遺産分割協議を経ずに受け取ることができます。相続手続きを簡略化し、相続人間の争いを防ぐためにも、遺言書の活用を検討することをおすすめします。
まとめ
高額介護サービス費や高額療養費制度の未支給分は、被相続人が生前に申請していれば相続財産となり、相続人が請求できます。しかし、申請期限は2年以内と定められており、早めの対応が必要です。また、給付金が相続財産に含まれる場合、遺産分割協議が必要となるため、相続人間での話し合いが重要になります。事前に遺言書で指定しておけば、手続きをスムーズに進めることができます。行政書士井戸規光生事務所では、相続診断士の資格を持つ行政書士が、相続発生後の手続きや遺言書の作成をサポートしております。未支給分の請求手続きや、遺産分割協議書の作成もお手伝いできます。初回の無料相談を実施中です! お電話052-602-9061またはEメールido.kimioアットマークofficeido.com、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。あなたの大切な財産を適切に引き継ぐため、全力でサポートいたします。