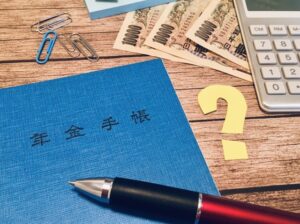受付時間:平日9時〜19時
婚姻に縛られない選択肢を!ファミリーシップ制度のポイントとは?

結婚という枠組みにとらわれず、自分たちらしい家族の形を選ぶ――そんな自由をサポートする新たな制度が「ファミリーシップ制度」です。この制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的効力は伴いませんが、行政が関係を認めることで社会的理解や実生活での利便性を高める狙いがあります。性的少数者や事実婚カップルをはじめとする多様な人々が対象で、宣誓手続きはシンプルながらも温かい配慮が施されています。このブログでは、ファミリーシップ制度の背景や具体的な内容、利用のポイントについて詳しく解説していきます。
ファミリーシップ制度とは?
ファミリーシップ制度とは、結婚や養子縁組といった法的枠組みを利用できない人々が、互いを人生のパートナーとして認め合い、安定した共同生活を築くことを支援する制度です。この制度は、性的少数者(LGBTQ+)や事実婚カップル、さらには近親者を含む多様な家族関係を対象とし、それぞれの事情に応じた柔軟な家族の形を行政が認める仕組みとして注目されています。
多様な人々を対象に
対象者は、同性・異性を問わず、パートナーとしての関係を築きたい人々です。婚姻や法的な養子縁組が難しいケースや、パートナーとの関係を公的に証明したいと考える方々が利用できます。宣誓を通じて、市区町村や都道府県から受領証明書などが発行され、社会的認知が得られるだけでなく、行政や民間サービスの利用も円滑になります。
制度導入の背景
この制度は、多様性を尊重し、人権を守る社会を目指して導入されました。性的指向や性自認による差別をなくし、家族形態の多様化をサポートすることが重要視されています。特に、名古屋市や愛知県では、住民が安心して暮らせる環境づくりの一環として、法律の枠を超えた新しい支援策として制度化されました。
ファミリーシップ制度の意義
法的効力がない理由と制度の価値
ファミリーシップ制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的効力を持ちません。つまり、相続権や税制上の優遇措置といった婚姻に伴う法的な権利義務は発生しない仕組みです。この背景には、現行の民法が同性婚や事実婚に対する法的認知を行っていないという現実があります。しかし、それでもこの制度が重要である理由は、「社会的認知」を得ることが当事者に大きな安心感を与え、彼らが社会で生きやすくなる環境を作る点にあります。
社会的認知の重要性
法的効力がないとはいえ、行政がパートナーシップや家族関係を正式に認めることで、社会における「家族」の多様性が広がります。これにより、たとえ法律上の婚姻が成立しなくても、職場や学校、医療機関などで家族として扱われる可能性が高まります。特に、性的少数者や事実婚カップルにとって、自らの関係を他者に説明する際に、行政の認証は説得力を持つ重要なツールとなります。
利用可能な行政・民間サービス
ファミリーシップ制度を活用することで、行政サービスや民間の家族向け特典を受ける機会が増えます。例えば、名古屋市や愛知県では、宣誓を行った2人が公営住宅の入居や緊急時の医療情報共有といったサービスを利用できるよう配慮されています。(ファクトチェック)また、民間企業でも福利厚生の対象としてファミリーシップを認める動きが広がっており、当事者が生活をより安定させるための一助となっています。 このように、法的効力がなくとも、制度が提供する社会的価値は計り知れないものがあるのです。
名古屋市・愛知県の取り組み
名古屋市ファミリーシップ制度の特徴
名古屋市では、2022年12月に「ファミリーシップ制度」を導入し、幅広いカップルが利用できる仕組みを整えています。この制度では、同性カップルや事実婚のカップルが、互いを人生のパートナーとして宣誓することで、市から「ファミリーシップ宣誓書受領証」などが発行されます。宣誓手続きにはオンラインと対面の両方が用意されており、特にオンライン対応は、遠方や身体的理由で市役所に出向けない方に配慮したものです。必要書類としては、住民票や独身証明書のほか、通称名を使用している場合はその確認書類が求められます。
愛知県ファミリーシップ宣誓制度の内容
一方で、愛知県は2024年4月から「ファミリーシップ宣誓制度」をスタートさせました。この制度の最大の特徴は、県内外のパートナーを柔軟に対象としている点です。具体的には、宣誓者のどちらか一方が愛知県に住んでいる、または転入予定である場合も対象とされるため、制度の利用範囲が広がっています。また、同居の有無にかかわらず、関係性が尊重される仕組みが整備されています。さらに、愛知県ではオンラインでの手続きも可能であり、宣誓に必要な書類には、住民票や独身証明書に加えて、近親者の記載を希望する場合の同意書などが含まれます。また、外国籍の方も利用できるよう配慮されており、国際的なカップルへの対応も行っています。これらの地域ごとの取り組みは、制度利用者がそれぞれの生活環境や状況に応じて選択できるよう、柔軟性と利便性を重視して構築されています。
宣誓手続きの流れと注意点
ここでは、名古屋市における手続きの流れを注意点について解説します。
宣誓の流れ
名古屋市のファミリーシップ制度では、まず宣誓日の予約が必要です。宣誓希望日の3か月前から1週間前までに、専用の申込フォームや電話を利用して予約を行います。その際、宣誓者の氏名や連絡先、希望する宣誓方法(オンラインまたは対面)を伝える必要があります。
宣誓時には、住民票や独身証明書などの必要書類を提出します。オンライン宣誓の場合は、書類を事前に郵送し、Zoomを利用して宣誓を行います。一方、対面宣誓の場合は、名古屋市の指定する場所において、必要書類を持参の上、職員立ち会いのもとで宣誓を行います。
宣誓時の注意事項
注意すべき点は、宣誓者二人がそれぞれ手続きを行い、両者の準備が完了していなければならないことです。また、オンライン宣誓では、顔写真付きの本人確認書類と、3か月以内に撮影した顔写真が必要です。不備がある場合は、再提出を求められることがあります。
宣誓後に得られる受領証明書とその活用例
宣誓が完了すると、「ファミリーシップ宣誓書受領証」と「受領証明カード」が交付されます。これらは、公営住宅の申請や医療機関での情報共有など、名古屋市内の行政サービスを利用する際に提示することで、家族としての認知を受けられる重要な証明書となります。
制度の課題と期待
法的効力がないことによる課題
ファミリーシップ制度は、法的効力を伴わないため、相続権や税制上の優遇といった婚姻関係における法的保護を受けられません。このため、パートナーが亡くなった場合に相続権が認められない、また税金の控除が適用されないといった現実的な問題が残ります。
利用者からの期待や要望
利用者からは、制度が法的効力を持つよう改善を求める声や、さらに多くの行政・民間サービスで利用できる仕組みの拡充を期待する意見が寄せられています。また、手続きのさらなる簡略化や、全国的な制度連携への要望も高まっています。
今後の展望
今後は、他自治体への制度拡大や、自治体間の連携による利便性向上が期待されています。また、ファミリーシップ制度の普及が社会全体での多様性理解を促進し、新しい家族の形が受け入れられる文化の醸成につながるでしょう。
まとめ: 多様な家族の形を認める社会へ
ファミリーシップ制度は、多様な家族の形を公的に認めることで、人々に安心感と希望をもたらします。自分らしい生き方を選ぶ重要性が増す現代社会において、誰もが平等に尊重される社会の実現に向けた大きな一歩です。
行政書士井戸 規光生事務所では、ファミリーシップ制度を検討する方々に対し、手続き支援や書類作成の代行などで貢献いたします。具体的には、必要書類の準備サポート、宣誓手続きの流れに関する相談などを行います。また、法的効力がない今の制度の補完として、公正証書遺言や任意後見契約書を作成し、財産管理や相続に備えるサポートを提供することも可能です。行政書士を活用することで、より安心して制度を利用できる環境が整います。初回相談は無料でございます。ぜひお気軽に、お電話(052-602-9061)、FAX(050-1545-5775)、お問い合わせフォーム、もしくはEメール ido.kimioアットマークofficeido からご相談ください。ご連絡お待ちしております。