受付時間:平日9時〜19時
認知症になる前に!遺言書と家族信託で守る財産と家族の未来
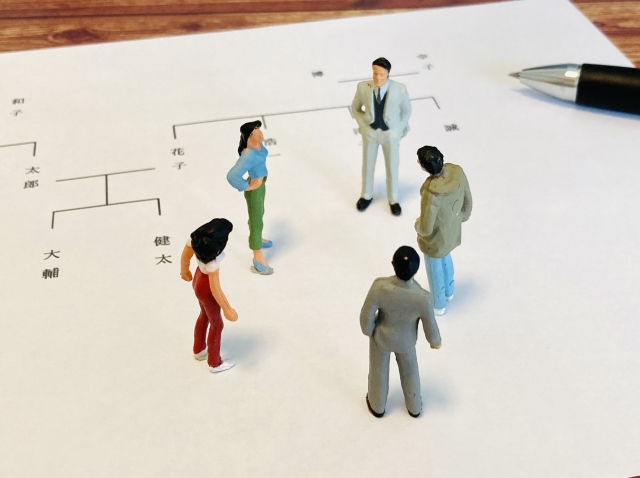
「うちは財産もそんなに多くないし、相続対策なんて必要ない」と思っていませんか? しかし、認知症のリスクは誰にでもあり、発症後には財産管理や相続の手続きが一気に難しくなってしまいます。もし親が認知症になったら、銀行口座が凍結され、遺言書の作成もできなくなり、家族が財産を管理するのに苦労することになります。そんな事態を防ぐために、「遺言書」と「家族信託」 が有効な対策となります。この記事では、認知症になる前にできる相続対策の重要性と、遺言書・家族信託を活用するメリットについて分かりやすく解説します。家族の未来を守るために、今からできる準備を一緒に考えてみましょう。
認知症と相続の関係 – なぜ対策が必要なのか?
認知症は誰にでも起こりうる問題
認知症は高齢者だけの問題ではなく、誰にでも起こりうるリスクです。内閣府によると2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると推計されており、加齢とともにそのリスクはさらに高まります。
認知症になると財産管理ができなくなる
認知症が進行すると、銀行口座の管理や不動産の売却ができなくなることがあります。家族が代理で手続きを進めようとしても、本人の意思確認が取れなければ、口座は凍結され、資産が動かせなくなる可能性があります。
遺言書が作れなくなる
これまでも、「相続対策に最も有効なのは事前の遺言書作成」と繰り返しお伝えしてきましたが、遺言書を作成するには、**「意思能力」**が必要です。認知症が進行し、法律的に意思能力がないと判断されると、遺言書の作成や変更が認められなくなります。その結果、相続争いの原因となることもあります。つまり「(遺言書なんて)まだ大丈夫」と語る方々の多くは既に遺言書を書くべきタイミングを迎えています。
親の財産が凍結されるリスクと、家族が困るケース
例えば、親が認知症を発症し、介護費用を捻出するために不動産を売却しようとしても、本人の判断能力が不十分な場合、売却ができません。さらに、成年後見制度を利用すると、家族の自由な財産管理が制限されることもあります。このような事態を避けるためにも、認知症になる前の相続対策として、遺言書作成と、家族信託契約が重要なのです。
遺言書でできること – 「認知症になる前」に作るべき理由
遺言書があれば、財産の分け方を明確にできる
認知症になると、自分の意思で財産の分け方を決めることができなくなります。遺言書がない場合、法定相続分に基づいて財産が分配されますが、これは必ずしも本人の希望に沿うものとは限りません。特に、介護をしてくれた子どもに多めに渡したい場合や、特定の人に財産を託したい場合、遺言書を作成しておくことで希望を反映させることができます。
相続トラブルを防ぐ効果がある
認知症になると、家族が本人の意思を確認することができなくなり、相続人同士の話し合いが難航するケースが増えます。財産分割の方針が決まらず、遺産分割協議がまとまらないと、家庭裁判所での調停や裁判に発展することもあります。遺言書を残しておけば、あらかじめ相続の方針が決まっているため、家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。認知症が進行してしまうと、自筆証書遺言は無効となるリスクが高くなります。なぜなら、遺言書が作成された時点で意思能力があったかどうかが争点になりやすく、相続人が遺言の有効性を巡って争うことがあるからです。一方、公正証書遺言は、公証人が関与するため、意思能力があったことが証明されやすく、安全性が高いのが特徴です。
公正証書遺言のメリット(認知症リスクがある人におすすめ)
認知症リスクを考えると、公正証書遺言の作成が特に有効です。公正証書遺言なら、公証人が本人の意思能力を確認しながら作成するため、認知症が軽度の場合でも、判断能力があるうちに作成できる可能性が高くなります。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。認知症が進行した後では、新たに遺言を作ることはできないため、早めの対策が家族の安心につながります。
家族信託とは?成年後見制度と何が違うのか?
認知症対策としての「家族信託」の仕組み
家族信託とは、財産の管理や運用を信頼できる家族に託す仕組みです。親が元気なうちに、自分の財産を信託契約で家族に託しておくことで、認知症になってもスムーズに財産管理が継続できます。特に、銀行口座の凍結や不動産の売却ができなくなるリスクを回避できるため、認知症対策として注目されています。
「成年後見制度」との違い(自由度・コスト・手間)
成年後見制度は、家庭裁判所が選任した後見人が財産を管理する制度ですが、一度始まると自由な財産運用が制限されるデメリットがあります。一方、家族信託は、本人の希望に沿った柔軟な財産管理が可能です。また、成年後見制度は裁判所への報告義務があり手間がかかるのに対し、家族信託は家族内で管理できるため手続きが簡単で、長期的なコストも抑えられます。
家族信託を活用するとできること(不動産管理・財産運用)
家族信託を利用すると、親が認知症になっても、信託契約に基づいて家族が不動産を売却したり、賃貸経営を続けたりできるため、資産を有効活用できます。また、株式や投資信託の運用を続けることも可能で、認知症による資産凍結のリスクを回避できます。
具体的な活用事例(親の財産を管理しながら生活費を確保)
例えば、賃貸物件を所有する親が家族信託を活用すれば、子どもが代わりに家賃収入を管理し、親の介護費用に充てることができます。認知症が進行しても、家族が柔軟に財産を運用し、親の生活を支えることができるのが家族信託の大きなメリットです。
遺言書と家族信託、どちらを選ぶべき?
遺言書が向いているケース(財産を分けるための手段)
遺言書は、相続人ごとに財産をどのように分けるかを明確に定めるための手段です。特に、特定の相続人に多めに遺産を残したい場合や、法定相続分とは異なる分配を希望する場合に有効です。また、遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、トラブルの原因になりやすいため、円満な相続を実現するために作成しておくと安心です。
家族信託が向いているケース(認知症になった後の財産管理)
家族信託は、本人が生きている間の財産管理に適した制度です。たとえば、認知症になって判断能力が低下すると、不動産の売却や銀行口座の管理ができなくなることがありますが、家族信託を活用すれば、家族が代わりに資産を管理・運用し、必要な支払いを行うことが可能になります。つまり、遺言書は「死後」の財産分割に適しているのに対し、家族信託は「生前」の財産管理に強みを持つ制度です。
両方を併用すると安心!バランスの良い相続対策とは?
遺言書は死後の財産の分配で、家族信託は生前の財産の管理と、それぞれ役割が異なるため、併用することでより安心な相続対策が可能になります。たとえば、家族信託で認知症リスクに備え、財産管理を家族に任せつつ、遺言書で最終的な相続の方針を決めておくことで、生前も死後もスムーズな資産承継が実現できます。どちらが必要か迷ったら、専門家に相談し、自分に合った対策を選ぶことが大切です。
まとめ – 早めの準備で家族を守る
認知症になってからでは、遺言書の作成も家族信託契約の締結もできません。その結果、財産が凍結され、家族が管理や相続手続きに苦労することになります。大切なのは、元気なうちに対策を始めることです。遺言書を作成すれば相続の方針が明確になり、家族信託を活用すれば認知症後の財産管理もスムーズになります。まずは専門家に相談し、自分や家族に合った生前対策を検討することが、将来の安心につながります。 行政書士井戸規光生事務所では、お客様のお困りごとに素早く、正確に対応し、最適な生前対策をご提案いたします。初回相談は無料ですので、「何から始めればいいかわからない」「認知症対策について詳しく知りたい」という方も、お電話(052-602-9061)、FAX(050-1545-5775)、お問い合わせフォーム、もしくはEメール ido.kimioアットマークofficeido からご相談ください。ご連絡お待ちしております。どうぞお気軽にご相談ください。






