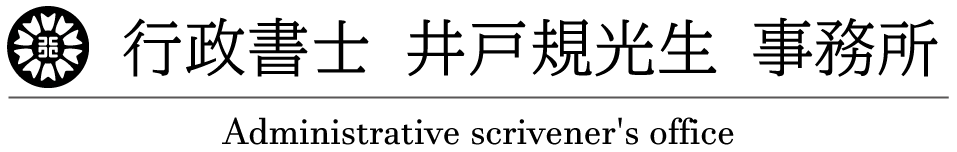受付時間:平日9時〜19時
養子縁組後の代襲相続、最高裁が初判断

はじめに
令和6年11月12日、最高裁判所は、養子縁組に伴う相続権の範囲についての重要な判断を下しました。この判決は、代襲相続の重要な論点に一石を投じるものです。代襲相続は、相続予定者がすでに亡くなっている場合、その子どもが親に代わり相続権を得る制度ですが、養子縁組前の関係がどこまで考慮されるべきかは、これまで法律的な曖昧さが残っていました。今回の判決では、「養子縁組前に生まれた子どもが新たな親族関係に基づき代襲相続することはできない」とする初めての判断が示されました。この判断は、相続範囲の明確化を進めるとともに、今後の相続トラブルへの対応策を考える重要な機会ともなります。
本記事では、この判決の概要と背景を詳しく解説し、今回の判断が相続実務に与える影響について考察します。さらに、相続を巡るトラブルを未然に防ぐための「遺言書」の重要性についても触れていきます。
代襲相続とは?
代襲相続とは、本来相続人となるべき人がすでに亡くなっている場合に、その子どもが親に代わって相続権を引き継ぐ制度です。甲、甲の子ども乙、乙の子ども丙がいた(配偶者や兄弟はいないものとします)場合、甲が亡くなった際にその子である乙がすでに他界している場合、丙が乙の遺産を相続することができます。これは、遺産がより近い血縁者に渡るようにするための法律的な仕組みです。
「直系型」と「傍系型」
代襲相続には「直系型」と「傍系型」という2つのパターンがあります。直系型は、祖父母から子どもへ、さらにその孫へと血縁が続くケースです。一般的に多くの家庭で該当するのがこの直系型で、民法上も明確に規定されています。一方、傍系型は叔父や叔母が亡くなった場合に、その甥や姪が相続するケースを指します。この場合、血縁が縦方向(直系)ではなく横方向(傍系)に広がります。
代襲相続が適用される条件としては、以下の2点が挙げられます。まず、本来の相続人が相続開始前に死亡していること。そして、本来の相続人が被相続人の子どもである場合、代襲相続が認められます。親Aには子Bがいて、子Bにも子C(Aから見ると孫)がいる場合。先にBが亡くなっていて、その後にAが亡くなった場合、CはBが持っていたAの相続権を引き継ぐという仕組みです。
ただし、孫以外の直系ではない親族に適用されるかどうか、兄Aと弟Bがいて、弟Bには子C(Aから見ると甥姪)などの場合については、法律上の曖昧さが残る場合もあります。代襲相続は、亡くなった人の遺志を継ぎ、次世代に財産を適切に渡すための大切な制度ですが、その範囲や適用条件についてはケースによって異なり、法律的な解釈が求められる場面も多いのが現状です。本記事では、この基本制度が今回の判決にどのように関係しているのかを解説します。
今回の事件概要
原告の主張
今回の裁判は、養子縁組と代襲相続の関係性を問う重要な問題が争点となりました。原告は、神奈川県に住む兄Aと妹Bで、母親Cが養子縁組をした際に新たな親族関係が生じたと主張しています。この母親Cは、生まれながらの親族関係であったおばにあたる女性Dの養子となり、Dの子であった男性Eとの関係性が「いとこ」から「兄妹」として再編された経緯がありました。その後、母親Dが亡くなり、次に男性Eが亡くなり、原告たち(A、B)は母親Dが持つはずだったEの遺産を代襲相続できると主張。母親が養子縁組をした後も、新しい親族関係は有効であり、その権利を自分たちが引き継ぐべきであると訴えました。
国側の反論
これに対し、国側は「養子縁組前に生まれた子どもA、Bは、養子縁組(A、Bの母Cが女性Dの養子になったこと)によって成立した、新たな親族関係の下で代襲相続をすることはできない」と反論しました。特に、民法上では代襲相続の適用範囲が祖父母から孫などの直系関係に明確に規定されている一方で、養子縁組後の傍系関係(叔父から甥など)に関する解釈には曖昧さが残っている点を強調しました。国側は、養子縁組後に関係が新たに設定されたとしても、代襲相続の範囲を必要以上に広げるべきではないとする立場を示しました。
判決の経緯
一審の横浜地裁では、原告の請求は退けられ、A、BにはEの遺産を代襲相続することはできないとされました。しかし、2023(令和5年)年1月の東京高裁では、原告の主張が認められ、一転して勝訴します。この判決は、代襲相続の適用範囲に関して、養子縁組後の関係を考慮すべきという新たな見解を示したものとして注目されました。しかし、最高裁は令和6年11月、東京高裁の判断を破棄し、「養子縁組前に生まれた子どもは代襲相続の対象外」とする判断を下しました。この結果、原告は逆転敗訴となり、今回のケースにおける代襲相続の適用は認められないことが確定しました。
この判決は、代襲相続と養子縁組の関係性に関する重要な解釈を提示したものとして、今後の相続実務に影響を与えることが予想されます。
最高裁の判断ポイント
最高裁は今回の判決で、民法の規定を厳格に適用し、相続の範囲を抑制的に判断しました。具体的には、養子縁組前に生まれた子どもが、新たな親族関係を持つかどうかという争点について、過去の判例を支持する形で「持たない」と結論付けました。この判断は、相続の範囲が広がりすぎることを防ぐためのものであり、被相続人の親の直系の子孫に限定されるべきという考えに基づいています。
裁判では、昭和7(1932)年の大審院の判例を引き合いに出し、養子縁組による新しい親族関係が養子縁組前の子どもには及ばない(もともと子どもA、BがいたCが、養子縁組をして、CとEが兄妹の関係になったからといって、A、BとEが、「甥姪と伯父」になったわけではない)とする解釈を採用しました。この結果、民法上曖昧とされていた部分が明確化され、養子縁組後の代襲相続について一定の制限が設けられたことになります。この厳格な解釈により、相続の範囲が無制限に広がることで発生する混乱やトラブルを防ぐ意図が反映された判断といえるでしょう。
判決の影響
傍系の代襲相続における制約が明確化
今回の判決は、相続実務において傍系親族の代襲相続に新たな指針を示しました。従来、叔父や叔母から甥や姪への代襲相続については、民法に明確な規定がないため、養子縁組など特殊な事情が絡む場合には判断が分かれるケースもありました。しかし、最高裁は「養子縁組前の子どもには新しい親族関係は生じない」とする厳格な解釈を適用し、代襲相続の範囲を限定しました。これにより、傍系親族が絡む複雑な相続トラブルの予防に役立つと考えられます。
養子縁組時の注意点が増加
さらに、今回の判決は、養子縁組の際に注意すべき点を浮き彫りにしました。養子縁組が新たな親族関係を形成するものである一方で、その影響が子どもたちに及ぶかどうかについて、法的な限界が存在することが明確化されたのです。特に、養子縁組後の相続において、代襲相続や相続分の調整が課題となる場合には、事前にその範囲を理解し、必要に応じて遺言書を作成することが不可欠となるでしょう。
トラブル防止に向けた新たな対策
この判決を受け、相続実務に携わる専門家は、養子縁組や傍系親族との相続に関して、より慎重な対応が求められることになります。また、養子縁組を予定している家庭では、自分たちの財産や家族構成を見直し、法的なリスクを事前に軽減するための対策を講じることが重要です。今回の判決は、法律の厳格な適用が実務に影響を与える好例といえるでしょう。
トラブルを防ぐためのポイント
今回の判決は、相続において「遺言書の有無」が重要な役割を果たすことを改めて示しました。特に、相続関係が通常よりも複雑な家庭の場合、遺言書がなければ法的な規定に基づいて判断されるため、想定外の結果になる可能性があります。遺言書を作成することで、財産の分配や相続人の指定について具体的な意思を反映させることができ、不要なトラブルを防ぐことができます。
今回のケースでは被相続人Eの生前の意思は明らかではありませんが、仮にEが「自分の死後は、A、Bが法定相続人になる」と信じていて、遺言書を残していなかった場合、Eの意思は最終的には反映されなかったことになります。
まとめ
今回の最高裁判決は、養子縁組や代襲相続に関する法律の解釈を明確化し、相続実務に大きな影響を与えるものでした。特に、養子縁組が相続関係に与える影響を正しく理解することが、家族間のトラブルを未然に防ぐために不可欠であることを示しています。こうした背景から、相続が発生する前に、家族の状況を整理し、適切な準備を進めることの重要性が一層高まっています。
相続に関して不明点や不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。井戸 規光生 行政書士 事務所は、遺言書の作成や相続手続きに関する豊富な知識と経験を持ち、一人ひとりの状況に応じたアドバイスを提供することが可能です。将来的な相続を見据えた養子縁組をお考えの方にも、最終的にどのような結果にしたいのかを確認したうえで、今取るべき適切な方法をご助言いたします。