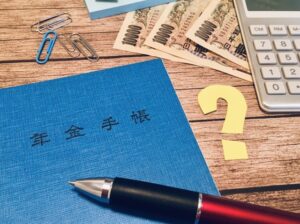受付時間:平日9時〜19時
遺言書をすぐに開封してはいけません!検認が必要な理由と手続きの進め方
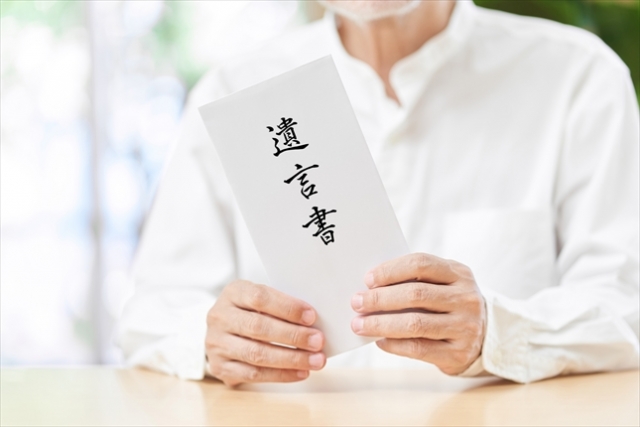
遺言書を発見した際、多くの方がすぐに開封して内容を確認したくなるかもしれません。しかし、実は遺言書の開封には注意が必要です。民法1004条では、遺言書の内容を確認する前に「検認」という手続きを行うことが義務付けられています。この手続きを怠ると、相続人間のトラブルやペナルティ(民法1005条では5万円以下の過料)が発生するリスクがあるのです。本記事では、検認が必要な理由とその具体的な進め方を解説します。遺言書の扱いを間違えると、大切な家族に思わぬ負担をかけることになりかねません。正しい手続きで、スムーズな相続を進めるためのポイントを押さえましょう。
遺言書を開封してはいけない理由
法律上のルール
遺言書を発見した場合、すぐに開封して内容を確認したいと考えるかもしれませんが、これは法律で制限されています。遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合、家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければなりません。検認は、遺言書の存在や内容を相続人全員に知らせ、遺言書が偽造・改ざんされることを防ぐための重要な手続きです。この検認を経ない状態で開封すると、遺言書の正確性や信頼性に疑念が生じ、相続人間のトラブルを引き起こす可能性があります。法律に従い、検認手続きを済ませることで、遺言書の効力を安全に確認し、相続手続きを進めることが求められます。
ペナルティのリスク
遺言書を無断で開封する行為には法律違反のリスクがあります。民法では、検認が必要な遺言書を家庭裁判所の許可なしに開封した場合、「5万円以下の過料」が科される可能性があると定められています。さらに、相続人間で遺言書の信頼性を損なう行為とみなされ、相続争いが激化する原因となることもあります。遺言書を発見したら、まずは家庭裁判所での検認手続きを行うべきです。これにより、相続人全員が公平に手続きを進められ、トラブルを未然に防ぐことができます。
検認が必要な遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆証書遺言には、法務局保管制度を使った場合と使わなかった場合に分けられます。それぞれの特徴と注意点を以下で解説します。
法務局保管制度を使った場合
法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は、遺言書の偽造や紛失を防ぐための安心な方法です。この制度では、遺言書が法務局で公的に保管されるため、検認手続きが不要になります。また、遺言書情報証明書が発行され、相続手続きで簡単に利用できるのも大きなメリットです。
法務局保管制度を使わなかった場合
法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。この手続きを通じて、遺言書の内容や形状を確認し、相続人全員にその存在を知らせます。ただし、検認を経ても遺言書の有効性が保証されるわけではないため、内容が法律に違反していないかを専門家に確認しておくことが重要です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう形式の遺言書です。この形式では、遺言書の保管が本人の手に委ねられるため、家庭裁判所の検認が必要になります。検認の目的は、遺言書が適切に保管され、改ざんが行われていないことを確認することにあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、内容を記録して作成されるため、検認は不要です。この形式では、公証人が作成時に法的な不備を確認し、遺言書を公証役場で保管します。そのため、偽造や紛失のリスクがなく、家庭裁判所での検認手続きが省略されます。手続きの簡便さや信頼性の高さから、公正証書遺言はトラブルを避けるための有効な手段として推奨されます。
遺言書の形式によって検認の有無が異なるため、遺言書を作成する際は、自身の状況に最適な形式を選ぶことが大切です。
検認手続きの具体的な流れ
家庭裁判所への申し立て
検認手続きは、遺言書を家庭裁判所に提出し、申し立てることから始まります。必要書類として、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、遺言書そのもの、申し立て書などが求められます。申し立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行い、不備がないよう事前に書類を確認することが大切です。
くわしくは裁判所のサイトからご確認ください
検認期日の通知と当日の流れ
家庭裁判所に申し立てを行うと、数週間から1か月程度した後に、検認を行う期日が通知されます。この日には、申し立て人だけでなく、他の相続人も立ち会うことが可能です。(申し立て人以外の相続人は立ち会えなくても問題ありません)当日は、裁判官が遺言書を開封し、内容や形状、加除訂正の有無を確認します。封印のある遺言書は特に重要で、家庭裁判所で開封しなければならないため、注意が必要です。
検認後の手続き
検認が完了すると、検認済証明書が発行されます。この証明書は、不動産の名義変更や預貯金の解約など、相続手続きを進める際に必要となる重要な書類です。検認手続きは、スムーズな相続を進めるための第一歩であり、早めに対応することが求められます。
「検認したから遺言書は有効」ではないことに注意
遺言書の検認は、あくまで「遺言書が存在することと、その状態」を確認するもので、これによって、偽造防止となり、その後の相続手続きに使えるということです。検認について多くの方が誤解されますが、検認したからといって、遺言が有効である、という意味ではありません。検認した後に遺言書の無効を主張したい際(*)には、遺言無効確認の話し合いや調停・訴訟を行う必要があります。
(*)例えば、「書いたときは認知症が進行していたのではないか」や、「書かれている相続人の一部は亡くなっているから、遺言書全体が無効」や、「書かれている財産の一部は失われているから、遺言書全体が無効」などの主張が考えられます。
実例解説
配偶者も、子どもも、孫も、親も、祖父母も既に亡く、兄弟姉妹3人と甥姪5人の合計8人が相続人というAさんがいました。兄弟姉妹は遠方に住んでいて疎遠で、甥姪も同様。しかしながら、甥のBさんとは交流があったので、Bさんに全財産を譲ることを記した遺言書をAさんは遺されました。 その後Aさんが亡くなり、遺言書も発見され、検認の日が相続人全員に通知されました。そして遠方の兄弟1人が現れて、自筆証書遺言の内容を知り、自分の相続分がゼロということを知り、「遺言書無効」の主張も辞さない姿勢を見せています…。 (事実を一部変更しております)このケースでは、自筆証書遺言保管制度を利用するか、公正証書遺言を書いておけば、すくなくとも検認手続きでの混乱はさけられました。
まとめ
遺言書の検認手続きは、相続を円滑に進めるために欠かせない重要なステップです。検認は、遺言書の内容を相続人全員に通知し、その正当性を確認することで、不正やトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認を経なければ相続手続きが進められない場合があります。不動産の名義変更や預貯金の解約ができず、相続人間での信頼関係が損なわれるリスクも生じます。検認手続きの必要性を正しく理解し、専門家のアドバイスを得ながら対応することで、スムーズな相続を実現しましょう。 行政書士井戸規光生事務所では、相続診断士の資格を有する行政書士が、ご依頼者様一人ひとりの状況に合わせて、遺言書作成のサポートを行っております。遺言書作成の際には、どのような形式の遺言書が一番適しているかのご助言も行っております。また、ご親族の死後に、遺言書が発見された場合も、その遺言書の扱い方の助言や、検認手続きのために必要な書類の収集も代行いたします。初回相談は無料でございます。ぜひお気軽に、お電話(052-602-9061)、FAX(050-1545-5775)、お問い合わせフォーム、もしくはEメール ido.kimioアットマークofficeido からご相談ください。
ご連絡お待ちしております。