受付時間:平日9時〜19時
遺族年金は誰がいくら受け取れる?知らないと困る基礎知識ガイド
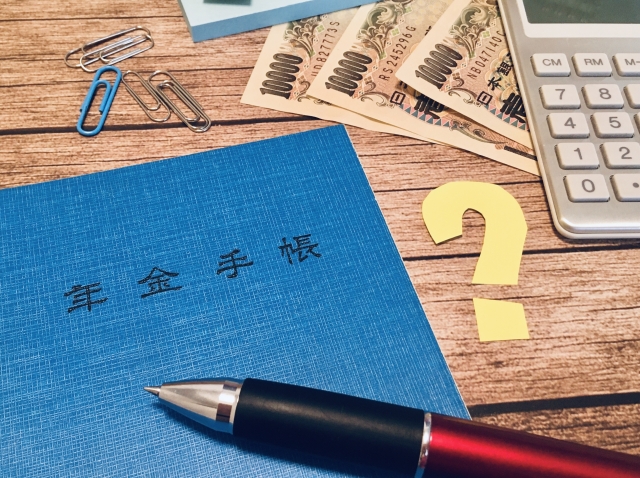
もし家族の大黒柱が突然亡くなったら、残された家族の生活をどう守るべきか、多くの人が不安に思うでしょう。その時、公的な保障制度である「遺族年金」が大きな助けとなります。しかし、「誰が」「どれくらい」受け取れるのか、その仕組みは意外と複雑で、知っているようで知らない部分も多いものです。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」という2種類があります。本記事では、遺族年金の基本的な仕組みを分かりやすく解説します。大切な家族のために、今から備えておきたい方はぜひご一読ください。
遺族年金とは?
遺族年金とは、家族の主な収入源となる人が亡くなった際、残された配偶者や子供の生活を支えるための公的年金制度の一部です。この制度は、遺族が経済的に困窮することを防ぎ、生活の安定を図ることを目的としています。遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、被保険者が国民年金や厚生年金に加入していたかどうかによって受給資格や支給額が異なります。公的年金制度の中で遺族年金は、大切な家族を守るための重要な役割を担っています。
遺族基礎年金の仕組み
遺族基礎年金とは?
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者が亡くなった際に、生活を支えるために残された家族に支給される公的年金です。この制度は、特に18歳未満の子供がいる家庭の生活安定を目的としています。
受給資格(加入要件と未納制限)
遺族基礎年金を受け取るためには、亡くなった人が国民年金に一定期間加入していたことが必要です。
1.国民年金被保険者の死亡
2.国民年金の被保険者だった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある人の死亡
3.国民年金の受給資格期間が25年以上ある人の死亡
1.2.の場合は、死亡日の前々月までに保険料納付済の期間が加入期間全体の3分の2以上。または、死亡日の前々月までの1年間に未納がない。という条件もあります。
③支給対象者と支給額の計算方法
遺族基礎年金の支給対象者は
1.18歳になった年度の末尾(3月31日)を過ぎていない子供がいる配偶者
2.20歳未満で1級・2級の障害を持つ子供がいる配偶者
3.18歳になった年度の末尾(3月31日)を過ぎていない子供
4.20歳未満で1級・2級の障害を持つ子供
です。2024年度の支給額は、配偶者と子供1人の場合で約102万円です。子供が2人以上いる場合、2人目には約23万円、3人目以降には約8万円が加算されます。
遺族厚生年金の仕組み
遺族厚生年金とは?
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金です。主に会社員や公務員など厚生年金の被保険者であった人の遺族が対象で、生活の安定を目的とした制度です。この年金は、遺族基礎年金と併せて支給される場合もあります。遺族厚生年金は厚生年金加入者を対象としています。また、遺族基礎年金が基本的に18歳未満の子供のいる家庭に限定されるのに対し、遺族厚生年金は配偶者や子供以外にも、一定条件を満たす父母や孫も対象となる場合があります。
受給資格
遺族厚生年金を受給するには、亡くなった人が厚生年金に加入中か、老齢厚生年金の受給資格を満たしていたことが必要です。
1.厚生年金加入中の者の死亡
2.厚生年金加入期間中に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡
3.1級または2級の障害厚生年金を受給中の人の死亡
4.厚生年金の受給権利者、または受給資格を満たした者の死亡
加入対象者
支給対象者は主に配偶者と子供ですが、一定の要件を満たす父母や孫、祖父母も含まれることがあります。
1.妻
2.18歳になった年度の末尾(3月31日)を過ぎていない子、孫
3.20歳未満で1級・2級の障害を持つ子、孫
4.55歳以上の夫、父母、祖父母
(30歳未満で、子がいない妻は5年限定)
(夫、父母、祖父母の支給は60歳から)
支給額の計算方法とポイント
支給額は、亡くなった人が受け取るはずだった老齢厚生年金額の4分の3に相当します。また、18歳未満の子供がいる場合、遺族基礎年金と合わせて支給されるため、家族構成によって実際の受給額が変動します。
制度改正の最新情報
遺族厚生年金の見直しポイント
現行制度では、子のない妻が夫に先立たれた場合、年齢に関係なく遺族厚生年金が支給される一方で、子のない夫は55歳未満だと遺族厚生年金を受け取る権利が発生しません。
この背景には、専業主婦の割合が高かった時代に、妻が夫に先立たれると生活に困る可能性が高いという考えがありました。しかし、現在では女性の就業率が高まり、共働き世帯が増加するなど、社会情勢が大きく変化したため、現行制度における極端な男女差を維持する必要性は薄れてきています。これを受け、2025年から遺族厚生年金の制度改正が進められる方向で議論されています。
遺族年金の申請手続き
③申請のタイミングと必要書類
遺族年金を申請するには、死亡した方の年金加入状況や遺族の関係性に基づき、速やかに手続きを行う必要があります。申請の際には、年金手帳や死亡診断書、戸籍謄本、住民票、金融機関の口座情報などに加え、12枚つづりの年金請求書が必要です。必要書類は状況によって異なるため、事前に確認することが重要です。
よくある手続き上の注意点
手続きは原則としてお近くの年金事務所で行います。遺族年金の申請は、死亡日の翌日から起算して5年以内に行わないと時効となり、受給権を失ってしまうので注意が必要です。また、不備のある書類を提出すると手続きが遅れる可能性があるため、事前に詳細を確認してから申請することをお勧めします。
まとめ
遺族年金は、家族を失った後の生活を支える重要な制度です。特に、配偶者や子供が安定した生活を維持するために不可欠な役割を果たします。しかし、その仕組みは複雑で、受給資格や手続きの詳細を誤解すると、本来受け取れる年金を逃してしまう可能性があります。社会保険労務士などの専門家に相談することで、正確な情報をもとに適切な対応が可能となり、申請手続きの不備を防ぐことができます。 行政書士井戸 規光生事務所では、大切なご親族を亡くされて、急ぎの手続きに追われる方のサポートを行っております。遺族年金に関する疑問をお持ちの方にも、適切なご助言をすると共に、遺族年金問題に明るい社会保険労務士をご紹介することで、ご依頼者さまの負担が少ない形で、その後の手続きを進めてまいります。初回相談は無料でございます。ぜひお電話(052-602-9061)もしくは、Eメール ido.kimioアットマークofficeido.com、お問い合わせフォームなどからご連絡ください。お待ちしております。






