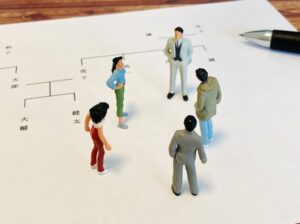受付時間:平日9時〜19時
相続した実家が“放置空き家”に… 行政代執行のリスクと生前対策とは?

相続した実家をそのままにしていませんか? 親から受け継いだ家が空き家のまま放置されると、思わぬトラブルを招くことがあります。特に、管理が行き届かず老朽化が進んだ場合、自治体から「特定空家」に指定される可能性があり、そのまま放置すると行政代執行によって強制的に解体されることも。しかも、その費用は所有者、つまり相続人が負担しなければなりません。さらに、空き家の維持管理や処分方法を巡って親族間で意見が対立し、相続トラブルに発展するケースも少なくありません。こうしたリスクを回避するためには、生前のうちに適切な対策を講じることが重要です。本記事では、行政代執行の仕組みやそのリスク、そしてスムーズに相続を進めるための生前対策について解説します。
相続した空き家、放置するとどうなる?
空き家を放置すると行政代執行の対象に?
「親の家を相続したけれど、誰も住む予定がない…」
このようなケースで空き家を長期間放置すると、行政から「特定空家」に指定される可能性があります。特定空家とは、建物の老朽化などにより倒壊の危険がある、または周囲の景観や衛生環境に悪影響を及ぼす空き家のことを指します。
行政代執行とは? どんなリスクがある?
特定空家に指定されると、市区町村から所有者に改善指導や勧告が行われ、それでも対応しない場合には、行政代執行が実施されることがあります。これは、自治体が強制的に建物を解体・撤去し、その費用を所有者に請求する制度です。この費用は数百万円に及ぶこともあり、相続人間のトラブルにつながるケースもあります。
事前にできる対策とは?
空き家の放置を防ぐためには、早めの管理や活用方法を検討することが重要です。売却や賃貸、解体などの選択肢を生前のうちに話し合い、適切な手続きを進めることで、空き家問題のリスクを回避できます。
行政代執行とは? 空き家所有者が直面するリスク
空き家の管理を怠るとどうなる?
空き家が適切に管理されず、老朽化や周囲への悪影響が進むと、市区町村から「管理不全空家」または「特定空家」に指定される可能性があります。特定空家と認定されると、自治体は所有者に対して助言や指導を行い、それでも改善されない場合は、勧告や命令を出すことになります。
行政代執行の影響は?
命令に従わず空き家を放置した場合、最終的に自治体が強制的に建物を撤去する「行政代執行」が行われます。この措置が実施されると、以下のような大きな負担が発生します。
✅ 自治体が強制的に解体!
✅ 解体費用は所有者負担!(数百万円以上かかることも)
✅ 相続人が複数いる場合、費用負担を巡りトラブルに発展!
一度執行されると避けられない
行政代執行は、あくまで最終手段ですが、いったん執行されると、所有者は拒否できません。さらに、解体費用は相続人に請求されるため、親族間の争いの火種にもなりかねません。こうしたリスクを回避するためにも、空き家の適切な管理や早期の処分を検討することが重要です。
空き家の放置は相続トラブルの原因
管理者不在で相続人同士が対立
空き家を相続したものの、誰が管理をするのか決まらないまま放置されると、相続人同士で意見が対立しやすくなります。特に、兄弟姉妹が複数いる場合、「自分は遠方に住んでいるから管理できない」「〇〇が住んでいたのだから管理すべきだ」などと責任を押し付け合うケースが少なくありません。結果として、適切な管理が行われず、建物の老朽化が進むことになります。
固定資産税の負担が不公平感を生む
空き家を所有しているだけで、毎年固定資産税がかかります。空き家の利用予定がない場合、この税負担を誰がどのように負担するのかを決めておかないと、「なぜ自分が払わなければならないのか?」といった不満が生じ、相続人同士の関係が悪化することもあります。さらに、特定空家に指定されると、固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、税負担が一気に増加する可能性もあります。
売却の難航で「負動産」化するリスク
売却しようとしても、老朽化が進んでいたり、立地条件が悪かったりすると買い手が見つからず、「負動産(不要な不動産)」となることがあります。売れないまま維持費だけがかかり続け、結局誰も手をつけられなくなるというケースも珍しくありません。こうした状況では、相続人の間で「売るべきか」「解体するべきか」と意見が分かれ、話し合いが難航することもあります。
空き家の放置は早めの対策が重要
こうしたトラブルを防ぐためには、相続前から空き家の管理・処分について話し合っておくことが大切です。生前に売却や活用方法を検討し、遺言書などで具体的な指示を残すことで、相続後の争いを未然に防ぐことができます。
空き家の行政代執行を避けるための生前対策
生前に売却・活用を検討する
空き家を放置すれば、老朽化が進み、やがて特定空家に指定される可能性があります。これを防ぐために、親が元気なうちに売却や活用を検討することが重要です。例えば、賃貸として貸し出す、リフォームして資産価値を上げる、または更地にして売却するなど、早めに方針を決めておけば、相続後の管理負担を軽減できます。
遺言書で空き家の処分方法を明確に
相続人同士で「どうするか決まらない」という状況を避けるためには、遺言書を作成し、空き家の処分方法を明記しておくことが有効です。例えば、「〇〇に売却を任せる」「△△が住むことにする」といった具体的な指示を残しておけば、相続後のトラブルを未然に防ぐことができます。
相続後の管理者を決めておく
空き家を相続した場合、「誰が管理するのか」を明確に決めておかないと、結局誰も手をつけずに放置されることになります。そのため、家族で話し合い、管理者を決めておくことが大切です。特に、遠方に住む相続人がいる場合は、現実的に管理が可能かどうかも考慮する必要があります。
相続登記を早めに済ませる
2024年4月から相続登記が義務化されるため、名義変更を後回しにすることはできません。相続登記を放置すると、登記名義人が増え、管理や売却がより難しくなる可能性があります。早めに手続きを済ませることで、スムーズな空き家対策が可能になります。
専門家に相談して適切な対策を
空き家の処分や管理に関する選択肢は多岐にわたるため、行政書士に相談することで、最適な対策を講じることができます。行政代執行という最悪の事態を防ぐためにも、生前から準備を進めておくことが重要です。
まとめ:相続前から空き家問題に向き合おう!
「相続した家を放置していたら、行政代執行で強制解体された…」
このような事態を避けるためには、早めの生前対策がカギです。親が元気なうちに話し合い、遺言や相続対策を検討することで、将来のトラブルを防げます。不要な空き家は、売却や活用の可能性を探ることも重要です。空き家問題は、相続発生後では手遅れになることが多く、放置すれば管理負担や費用の面で大きなリスクを伴います。大切な財産を守るために、今すぐできる対策を始めましょう!行政書士井戸 規光生事務所ではご相談者様それぞれの事情に寄り添って遺言書作成補助業務や、相続手続き代行業務を行っております。 空き家問題が起こらないように生前対策をサポートしたり、空き家問題を既に抱えているお方にも最適の解決策を立案いたします。初回相談は無料ですので、「何から始めればいいかわからない」「認知症対策について詳しく知りたい」という方も、お電話(052-602-9061)、FAX(050-1545-5775)、お問い合わせフォーム、もしくはEメール ido.kimioアットマークofficeido からご相談ください。ご連絡お待ちしております。どうぞお気軽にご相談ください。